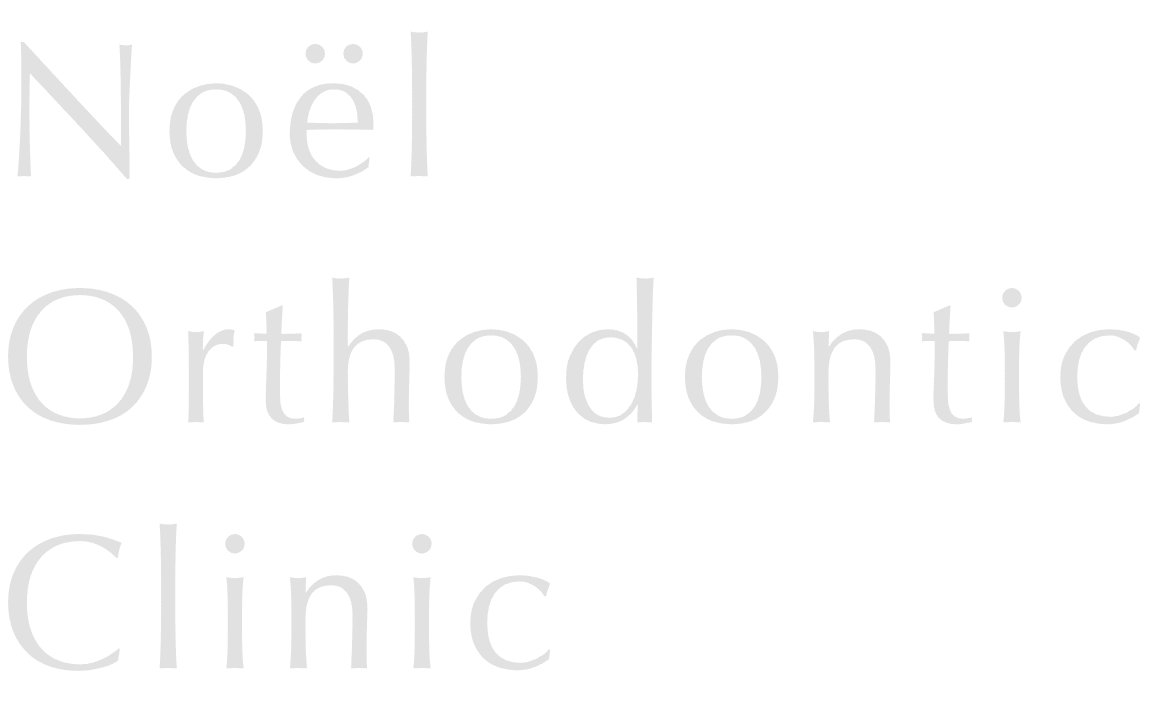ortho
歯並びの乱れの種類・
矯正治療のリスクや
副作用について
歯並びの乱れにも いろいろなパターンが あります
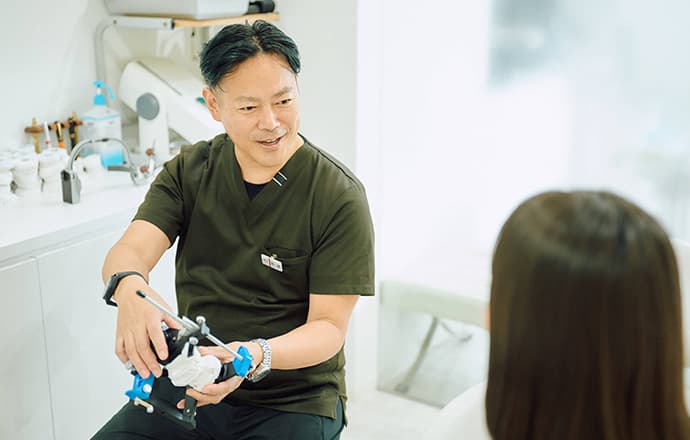
人それぞれに個性があるように、口腔内も十人十色です。きれいな歯並びの方もいれば、そうでない方もいらっしゃいます。中でも、歯並びやかみ合わせが乱れている状態を「不正咬合(ふせいこうごう)」と呼び、いくつかのタイプに分類されます。また、複数の不正咬合が組み合わさっている場合もあり、タイプによって治療方法や期間、最適な開始時期が異なります。
不正咬合は見た目の印象にとどまらず、発音や咀嚼機能、さらには全身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。
不正咬合の種類
叢生(そうせい)

歯が重なり合い、凸凹に生えている状態を「叢生」、または「乱ぐい歯」といいます。日本人に多い「八重歯」も叢生の一種です。歯が大きい、あるいは歯槽骨が小さいことで、歯並びが乱れて生えてしまいます。特に日本人の場合は、歯が大きいことが原因で叢生が生じるケースがほとんどです。
叢生は歯みがきがしにくく、虫歯や歯周病のリスクが高い歯並びです。そのため、矯正治療においては叢生の程度によって、永久歯の抜歯を伴う本格的な矯正治療が必要になることがあります。
「子どものうちにあごを拡げる装置を使えば歯を抜かずに済む」といった説明を耳にすることもありますが、実はこれを裏づける決定的なエビデンスはありません。非抜歯で歯が並べられるかどうかは、雰囲気やイメージではなく、精密検査の結果に基づいて慎重に判断する必要があります。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)症

いわゆる「出っ歯」と呼ばれる不正咬合です。日本人に多い傾向にあり、上の前歯が外側に傾いている場合や、上顎全体が前方に出ている場合、さらに下顎の骨が小さい場合などがあります。
子どもの上顎前突症では、下顎の成長が不十分なことが原因となっているケースが多いため、下顎の成長を促す治療(成長誘導)が有効なこともあります。最適な治療開始時期は、11歳から13歳頃です。
下顎前突(かがくぜんとつ)症

いわゆる「受け口」「反対咬合」と呼ばれる不正咬合で、下の前歯が上の前歯より前に出ている状態です。 この症状には、上の前歯が内側に傾いている場合、下の前歯が外側に傾いている場合、上顎骨が小さい場合、下顎骨が大きい場合など、さまざまな原因があります。
前歯の位置のずれによる下顎前突症には、早期治療が有効です。ただし、下顎前突症の治療は長期間におよぶことが多く、成人に近づくまで継続する場合もあります。
重度の場合は、矯正治療単独では対応が難しく、外科手術を併用した外科的矯正治療の適応となることがあります。
上下顎前突
(じょうかがくぜんとつ)症

上の前歯と下の前歯が共に外側に傾いている状態です。最近では「口ゴボ」とも呼ばれます。口元がとがり、唇が閉じにくくなるのが特徴です。食べ物がかみづらくなるだけでなく、口の中が乾燥しやすいため、虫歯や口臭などの原因になりやすいというデメリットもあります。
一見「きれいな歯並び」に見えることもありますが、前歯が外側に傾いているため、実は良いかみ合わせとは言えません。
上下顎前突症を治療するかどうかの主たる要因は、審美的な要望によることが多く、永久歯の抜歯を伴う矯正治療が必要となるケースがほとんどです。
開咬(かいこう)症

かんだときに奥歯だけがあたっていて、前歯がかみ合わず常に上下にすき間が開いている状態です。この状態では、食べ物(特に麺類など)をかみ切りにくく、口唇が閉じにくいため口が開きがちになります。
開咬症の主な原因は、口唇の筋力不足や舌小帯の硬さによって、舌が前歯を外側に押していることに起因していることが多いです。そのため、矯正治療によって歯の位置を機械的に整えるだけでなく、舌小帯切除などの処置を併用することも必要になります。
また、開咬症ではかむ力(およそ体重分の力)が奥歯に集中するため、奥歯が割れたり欠けたりするリスクが高くなります。開咬症は矯正治療の難易度が高い不正咬合のひとつですが、早期治療が有効とされているタイプでもあります。
過蓋咬合(かがいこうごう)

上の歯列が下の歯列を深く覆っている状態です。歯と歯が必要以上に接触しているため、歯のすり減りが生じやすくなります。
成人の過蓋咬合は治療の難易度が高く、矯正専門医院での対応が必要です。また、開咬症と同様に過蓋咬合も治療難易度が高い不正咬合であるため、早期の治療が有効とされています。
交叉咬合(こうさこうごう)

上下の奥歯がすれ違うようなかみ合わせの状態です。ほとんどの場合、第2大臼歯に生じます。
奥歯がかみ合わせに参加していないだけでなく、下顎の位置を制限するため、左右のバランスが崩れやすく、また1本前の第1大臼歯に負担がかかりやすい状態です。
空隙歯列(くうげきしれつ)

いわゆる「すきっ歯」と呼ばれる歯並びで、歯と歯の間に隙間がある状態です。歯が小さいことによって生じます。食べ物が挟まりやすいだけでなく、隙間に隣の歯が倒れ込むなど、歯並びがさらに乱れる原因となることもあります。
空隙歯列の場合、矯正治療後に補綴処置が必要となる場合があります。
不正咬合は 全身に影響を及ぼします

不正咬合は、単に歯並びやかみ合わせの問題にとどまらず、全身の健康にもさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。自覚がなくても、頭痛や肩こり、姿勢の乱れなど、身体の不調の原因が実は不正咬合によることも少なくありません。
- 食べ物をしっかり咀嚼できず胃腸に負担がかかる
- きれいに発音しづらくなる
- ケアが行き届かず、虫歯・歯周病になりやすくなる
- 汚れを落としにくいために口臭の原因になる
- 歯が折れやすくなる
- 食いしばれず力を入れにくくなる
- 顎の関節に負担がかかり顎関節症になる
- 肩こりや頭痛を引き起こす
また、身体的な問題だけでなく、コンプレックスなど精神的にも悪影響を及ぼすことがあります。
矯正治療のリスクや 副作用についてご案内

矯正治療のリスクとしては、
- 治療中は、不快感・痛みなどを感じる可能性があります。
- 虫歯や歯周病になりやすくなるため、ブラッシングを「とても」頑張る必要があります。
- 通院頻度、装置の使用状況など、患者様自身の治療への取り組みが重要です。これは治療成果や治療期間ならびにリスク因子に影響を及ぼします。
- 矯正治療中に、歯根が短くなったり(歯根吸収)、歯肉の退縮(ブラックトライアングル)が生じる可能性があります。
- 歯が骨性癒着しているなどが原因で、歯が動かない場合があります。
- 歯の状態によっては歯髄が失活する場合があります。
- 治療中に顎関節症状が強く出る場合があります。
- 歯の動き方には個人差があるため、治療期間が延長することがあります。
- 患者様の希望、装置の使用状況など種々の理由から治療計画を変更する場合があります。
- 矯正治療後に、補綴物のやりなおし(BuildUp)、歯の形態修正(Reshape)などが必要な場合があります。
- レントゲンやCT撮影時には、被爆の問題があります。
- 抜歯やアンカースクリューなど観血的処置が必要な場合があります。
- 金属アレルギーやラテックスアレルギーを発症することがあります。
- 装置を撤去する際に、歯の表面(エナメル質)に傷がつく場合があります。また被せ物が脱離することもあります。
- 顎の成長や加齢変化によって矯正治療後にも歯並び・かみ合わせは変化します。
- 矯正治療後は保定管理を継続的に行う必要があります。
- 一般歯科のかかりつけ医(ない場合はご紹介します)にも継続的に通院する必要があります。
- 何らかの理由により、矯正治療後に再治療が必要となる可能性があります。